2006/07/20 00:26:02
どうしたら楽器をもっと上手く吹くことが出来るのか?
奏者にとって、これは永遠に考え続けるテーマかもしれません。
では楽器が上手い人とはどんな人なのでしょうか?
それは間違いなく、機敏な人でしょう。
指揮者にその場で言われた指示などに
すぐに対応できない人がいますよね。
例えば「タイ無しで吹いて。」「16分音符分割で吹いて。」
と言われた時、最初数回間違えてしまうような人です。
もっと高度なのになると
「メトロノームを表拍だけならして、裏拍を表拍で吹いて!」
という指示です。
まあ、単純に初見が苦手と言う人や
指がなかなか回らない人もそうかもしれません。
私もかなり苦手な方です。
機敏な人とは、楽器を構えた瞬間集中力が、格段にあがり、どんな指示を出されても、即座に対応できる人です。
おそらく内面はスポーツ選手のように機敏ですばらしい反射神経のよさを持っています。
そういう人は本番以外でも、そう簡単にミスはしません。
ミスをしないのが当たり前という日ごろから感じで練習します。
また、反応のよさから多少の難しさや吹きにくさも、自分なりにコツをつかみ即座に対応してしまいます。
「しかし、そういう人は、生まれつき頭がよかったり、才能があるほんの一部の人でしょ?」
「瞬発力なんて、今から鍛えられないんじゃないの?」
そんな声が聞こえてきそうですが、心配ありません。
心がまえだけで修正できるミスは結構多いということを覚えておいてください。
楽器を吹いているときは常に一流奏者のイメージを頭に思い浮かべましょう!
現実とのギャップに思い悩む必要はありません。
自分に足りない所を具体的に意識するだけで、あなたはイメージである一流奏者に少しづつ近づくことができます。
「正しいアンブッシュア」「運指」などのテクニック系の要因はあくまでも楽器を吹く手段にすぎません。
音楽やいろいろな物に対し機敏になるクセをつけましょう。
自分の吹いた音や、他人の吹いた音などを、口に出さなくてもいいので
その都度、評価してみるのもいい訓練になります。
歌に関して言えば、私たちはみんな死ぬまで、学生なのよ
マリア・カラス
奏者にとって、これは永遠に考え続けるテーマかもしれません。
では楽器が上手い人とはどんな人なのでしょうか?
それは間違いなく、機敏な人でしょう。
指揮者にその場で言われた指示などに
すぐに対応できない人がいますよね。
例えば「タイ無しで吹いて。」「16分音符分割で吹いて。」
と言われた時、最初数回間違えてしまうような人です。
もっと高度なのになると
「メトロノームを表拍だけならして、裏拍を表拍で吹いて!」
という指示です。
まあ、単純に初見が苦手と言う人や
指がなかなか回らない人もそうかもしれません。
私もかなり苦手な方です。
機敏な人とは、楽器を構えた瞬間集中力が、格段にあがり、どんな指示を出されても、即座に対応できる人です。
おそらく内面はスポーツ選手のように機敏ですばらしい反射神経のよさを持っています。
そういう人は本番以外でも、そう簡単にミスはしません。
ミスをしないのが当たり前という日ごろから感じで練習します。
また、反応のよさから多少の難しさや吹きにくさも、自分なりにコツをつかみ即座に対応してしまいます。
「しかし、そういう人は、生まれつき頭がよかったり、才能があるほんの一部の人でしょ?」
「瞬発力なんて、今から鍛えられないんじゃないの?」
そんな声が聞こえてきそうですが、心配ありません。
心がまえだけで修正できるミスは結構多いということを覚えておいてください。
楽器を吹いているときは常に一流奏者のイメージを頭に思い浮かべましょう!
現実とのギャップに思い悩む必要はありません。
自分に足りない所を具体的に意識するだけで、あなたはイメージである一流奏者に少しづつ近づくことができます。
「正しいアンブッシュア」「運指」などのテクニック系の要因はあくまでも楽器を吹く手段にすぎません。
音楽やいろいろな物に対し機敏になるクセをつけましょう。
自分の吹いた音や、他人の吹いた音などを、口に出さなくてもいいので
その都度、評価してみるのもいい訓練になります。
歌に関して言えば、私たちはみんな死ぬまで、学生なのよ
マリア・カラス
PR
2006/07/15 09:04:51
まず合奏をする前に各個人が、ある程度吹けている事が前提です。
合奏は、個人の練習の場ではありません。
みんなで音を合わせる練習をするところです。
①徹底的に合わせる!
同じ動きをしている人たちの音が一つの音に聞こえるまで。
ピッチ、音程、息のスピード、音形
発音(アインザッツ)、処理(リリース)を完璧にあわせましょう。
その時に、誰かが音を出すのを待って入ったり
息を恐る恐る出す吹き方をしてはだめです(たとえpでも)。
しっかり吹いて、合わせましょう。
必要なのはコントロールする能力です。
②メロディーは伴奏を聞き、伴奏はメロディーを聞く。
低音の上に、中音、高音が乗っかる事でサウンドは成り立ちます。
三者がピッタリあえば、響き、音の迫力が格段に倍増します。
三者が分離してしまうと、互いの音をかき消し合い
せっかくの音の幅が半減してしまいます。
特に低音は一番下でバンド全員を支えています。
しっかり吹いて、サウンドを安定させてください。
合奏で一番大事なのは、なんとなく惰性の練習にならないこと。
毎日やっていても何も考えず吹いているだけでは
合奏はまったく効果がないです。
吹いてるうちに自然と楽器や周りが変わってきて
だんだん合ってくるということはほとんどありません。
自分を変えない事には何も変わらないです。
人気blogランキングへ
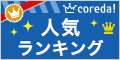

合奏は、個人の練習の場ではありません。
みんなで音を合わせる練習をするところです。
①徹底的に合わせる!
同じ動きをしている人たちの音が一つの音に聞こえるまで。
ピッチ、音程、息のスピード、音形
発音(アインザッツ)、処理(リリース)を完璧にあわせましょう。
その時に、誰かが音を出すのを待って入ったり
息を恐る恐る出す吹き方をしてはだめです(たとえpでも)。
しっかり吹いて、合わせましょう。
必要なのはコントロールする能力です。
②メロディーは伴奏を聞き、伴奏はメロディーを聞く。
低音の上に、中音、高音が乗っかる事でサウンドは成り立ちます。
三者がピッタリあえば、響き、音の迫力が格段に倍増します。
三者が分離してしまうと、互いの音をかき消し合い
せっかくの音の幅が半減してしまいます。
特に低音は一番下でバンド全員を支えています。
しっかり吹いて、サウンドを安定させてください。
合奏で一番大事なのは、なんとなく惰性の練習にならないこと。
毎日やっていても何も考えず吹いているだけでは
合奏はまったく効果がないです。
吹いてるうちに自然と楽器や周りが変わってきて
だんだん合ってくるということはほとんどありません。
自分を変えない事には何も変わらないです。
人気blogランキングへ





