2007/06/22 12:18:48
なぜロングトーンをするのか?
それは、楽器を吹く上で一番ストレスのない吹き方だからです。
つまり...
ちょっと酷な言い方をすれば...
ロングトーンでまともな音が出せないということは、何を吹いても曲になっていないということです。
指が引きつるような16部の連符だって、その音符の音一つ一つが真珠のようにつながって連符になっています。
ロングトーンができてない状態で、たとえ指が回ったとしても、綺麗な旋律は聞こえてきません。
ダミ声の人が、早口言葉をしゃべっても、それはダミ声ですね?
というわけで、面白くないことを言うようですが
ロングトーンを完璧にしないと、楽器の上達は、まず望めないでしょう。
また、ロングトーンにしても、ただ音を伸ばすだけの練習には
なってはいけません。
いろんなことを意識しながら吹きましょう。
まず音をまっすぐ伸ばす。
この一番の基本が出来ていない人が意外と結構いるのです。
伸ばしているうちにピッチが変わってきてしまう人
ピッチが定まらず、フラフラ揺れたピッチで吹く人
伸ばしているうちに音自体が減衰、音が細くなってしまう人
音色が、どんどん変わっていく人
音がだんだん広がっていく、息を押し込むような吹き方をする人
このような吹き方になってしまってると思う人は
意識して直してみてください。
ロングトーンは、楽器が変わっていくのではなく
自分が変わっていく練習です。
どうしたらもっといい音が出るのかと思い、試行錯誤をして
すばらしい音が出せるように自分自身が変わっていかなければいけません。
意識しないで、ただ音を伸ばすだけではロングトーンの効果は半減します。
人気blogランキングへ
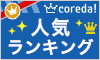

それは、楽器を吹く上で一番ストレスのない吹き方だからです。
つまり...
ちょっと酷な言い方をすれば...
ロングトーンでまともな音が出せないということは、何を吹いても曲になっていないということです。
指が引きつるような16部の連符だって、その音符の音一つ一つが真珠のようにつながって連符になっています。
ロングトーンができてない状態で、たとえ指が回ったとしても、綺麗な旋律は聞こえてきません。
ダミ声の人が、早口言葉をしゃべっても、それはダミ声ですね?
というわけで、面白くないことを言うようですが
ロングトーンを完璧にしないと、楽器の上達は、まず望めないでしょう。
また、ロングトーンにしても、ただ音を伸ばすだけの練習には
なってはいけません。
いろんなことを意識しながら吹きましょう。
まず音をまっすぐ伸ばす。
この一番の基本が出来ていない人が意外と結構いるのです。
伸ばしているうちにピッチが変わってきてしまう人
ピッチが定まらず、フラフラ揺れたピッチで吹く人
伸ばしているうちに音自体が減衰、音が細くなってしまう人
音色が、どんどん変わっていく人
音がだんだん広がっていく、息を押し込むような吹き方をする人
このような吹き方になってしまってると思う人は
意識して直してみてください。
ロングトーンは、楽器が変わっていくのではなく
自分が変わっていく練習です。
どうしたらもっといい音が出るのかと思い、試行錯誤をして
すばらしい音が出せるように自分自身が変わっていかなければいけません。
意識しないで、ただ音を伸ばすだけではロングトーンの効果は半減します。
人気blogランキングへ
PR
2007/06/21 14:39:38
これまで楽器を吹く上で基礎となる部分を紹介してきました。
ブレスコントロール、アンブシュア、身体のポジション、腹式呼吸などが、それに当たります。
しかし、いざ曲を吹いてみると
「あれだけ緻密にやってきた基礎練習の全てが吹っ飛んでしまう」
「基礎練習が曲、つまり実践に生かせていない!」
そう感じる演奏者が多いようです。
そう感じる人は、毎日の基礎練習がマンネリ化してきていないか確認しなければなりません。
何も考えずにロングトーンやスケール練習を続けても楽器は上達しません。
もっと多くのことに意識しましょう。
初心者の人はあまり難しく考えずに「さっきよりいい音で吹こう!」と意識して、自分の音に神経を集中してください。
ちなみに全国金賞の強豪校では、練習方法も柔軟に変化するそうです。
たとえば...
次に手がける曲の調のスケールを徹底的にしよう!
このリズムは課題曲でよく出てくるから、基礎練習に取り入れよう!
このハーモニーはなかなか合わないから合奏練習に取り入れよう!
こんな興味深い提案が、生徒の側からバンバン出るのです!
これが、音楽は一人で作るのでなくみんなで作るものだという言葉の意味なのです。
一人の耳より大勢の耳で演奏を改善しましょう!
基礎練習は、曲を吹くための練習です!
基礎練習で身につけたことを一つでも多く実際の演奏で発揮できるようにしましょう。
ブレスコントロール、アンブシュア、身体のポジション、腹式呼吸などが、それに当たります。
しかし、いざ曲を吹いてみると
「あれだけ緻密にやってきた基礎練習の全てが吹っ飛んでしまう」
「基礎練習が曲、つまり実践に生かせていない!」
そう感じる演奏者が多いようです。
そう感じる人は、毎日の基礎練習がマンネリ化してきていないか確認しなければなりません。
何も考えずにロングトーンやスケール練習を続けても楽器は上達しません。
もっと多くのことに意識しましょう。
初心者の人はあまり難しく考えずに「さっきよりいい音で吹こう!」と意識して、自分の音に神経を集中してください。
ちなみに全国金賞の強豪校では、練習方法も柔軟に変化するそうです。
たとえば...
次に手がける曲の調のスケールを徹底的にしよう!
このリズムは課題曲でよく出てくるから、基礎練習に取り入れよう!
このハーモニーはなかなか合わないから合奏練習に取り入れよう!
こんな興味深い提案が、生徒の側からバンバン出るのです!
これが、音楽は一人で作るのでなくみんなで作るものだという言葉の意味なのです。
一人の耳より大勢の耳で演奏を改善しましょう!
基礎練習は、曲を吹くための練習です!
基礎練習で身につけたことを一つでも多く実際の演奏で発揮できるようにしましょう。





